いつもとは違う一日
ポールは頭を上げ、かすかな焼けた臭いに鼻をひくつかせた。バスの中を見回したが、他の誰も気づいていないようだった。ポールの目は運転手に止まり、その手の甲はハンドルを握りしめ白くなっていた。もう十数分も走っていて、今さら引き返せはしない。


これは典型的な水曜の午後、午後3時ちょうど、10歳のポール・ウィティカーが学校バスに乗り、ポートランドの静かな通りを帰路につく――そんな普通の日だった。しかし、このバスが彼の運命を変える、忘れられない出来事に巻き込まれることになる。
いつものバスの帰り道
普段通りの午後だったはずの帰り道で、ポールの鋭い感覚と勇気が、彼を思いがけないヒーローへと導く。


午後3時きっかり、10歳のポールはいつもの席、二列目に腰を下ろした。だがすぐに、バス前方から強まる異臭に気づいた。眉を寄せ、不安を感じながら、隣の席のメーガンに小声でささやいた。
悪化する異臭
ポールは窓の外の好きなビデオゲームのことを考えながらぼんやりしていたが、突然、鋭く、知らない臭いがバスに漂ってきた。鼻をつく刺激臭で、それはこれまで嗅いだことのない強い匂いだった。不安が胸に押し寄せ、臭いはどんどん強くなってきていた。


周りを見ると、他の乗客は普段通り話したり本を読んでいたが、空気だけが重く感じられた。席に身を寄せ、ポールの鼓動が早まる。臭いは明らかにひどくなっている。気づいているのは自分だけなのか?彼は友達のメーガンにこんな匂いに気づいているか問いかけたかった。
広がるパニック
ポールはメーガンに向かって声を震わせた。「ねぇ、匂うよね?何かおかしいよ」 11歳のメーガンは頷き、その目には大きな不安が宿っていた。重く奇妙な臭いが二人を包み込み、見えない脅威のようだった。


理解し合う暇もなく、バスは突然ガクンと揺れた。乗客たちは席に体を投げ出され、リュックや本が飛び散る。子どもたちの間に一斉にパニックが巻き起こった。ポールは前の席の背もたれにつかまり、指先が白くなるほど力を込めた。胸が張り裂けそうな鼓動を感じ、前方を見つめた。いったい何が起きているのか?
明らかにおかしい
再びバスが揺れ、子どもたちはふらつき、恐怖で息を詰まらせた。ポールの胸は激しく脈打ち、彼の視線は前方にある運転席へ向かった。そこには、運転手のメアリー・ゴバンダーさんが、必死に車体を制御しようと格闘していた。何かが明らかにおかしかった。


ゴバンダーさんの手は震え、顔色は恐怖と混乱で青ざめていた。バスは車線を行き来し、タイヤはアスファルトを悲鳴のように擦っていた。彼女の足はブレーキペダルの上にありながら躊躇い、バスの制御に苦闘していた。
パニックに陥る運転手
パニックに陥った運転手は、ルームミラー越しに生徒たちを見つめ、恐怖に見開かれた目をしていた。彼女の声は震え、「みんな、席に座ったままでいてね?大丈夫、私がなんとかするから!」と訴えた。しかしメアリーの言葉はどこかろれつが回らず、視線も定まらず、体はふらふらと揺れていた。バスは道路脇に向かって揺れていた。


中では混乱が爆発した。子どもたちは叫び声を上げ、外を見て何が起きているのか必死に確認しようとしていた。運転手は必死に子どもたちを落ち着かせようとしたが、努力はむなしかった。 その中で、ポールは周囲の騒音が遠のくのを感じていた。奇妙で息苦しい臭いが空気を満たし、どんどん強くなっていた。彼の心臓は激しく鼓動を打ち、行動を起こさねばと直感していた。
緊急用の携帯電話
ポールはバックパックの中に手を伸ばし、両親から「こういう時のために」と渡されていた緊急用の携帯電話を取り出した。震える手で911をダイヤルし、鼓動の速さを感じながら耳に当てた。 「911、緊急通報です。どうされましたか?」と落ち着いた声が応答したが、ポールはしばらく言葉を失っていた。


深呼吸をしてようやく口を開いた。「こんにちは、ぼくの名前はポールです。ヒルズデール小学校の生徒です」と彼はつっかえながら名乗った。「スクールバスに異常があるんです!急に揺れたりして、運転手さんがすごく怖がってます!」
圧倒的な悪臭
オペレーターは冷静に対応しながら、ポールに現在地を尋ね、安心させようとした。その間にも、車掌が混乱した状況をなんとか抑えようとしていた。オペレーターは、事故に遭っていないか、運転手の様子についてさらに詳しく聞こうとした。 一方、バスの中は息が詰まりそうな悪臭で満たされ、ポールは咳き込み、目には涙が浮かんだ。


「これは本当にまずい」とポールは思った。時間との勝負だった。彼は携帯電話を強く握りしめ、恐怖と決意に手が震えていた。オペレーターの落ち着いた声が耳元で響き、それに支えられるように、彼は言葉を振り絞った。「バスの番号は564番で、キャニオン・ストリートにいます。運転手さんが、変なんです!」
操作を取り戻そうとする中で
バスが左右に大きく揺れる中、ポールの頬には涙が伝っていた。周囲ではクラスメートたちが必死に座席にしがみつき、泣き叫んでいた。ポールは携帯を握りしめながら、「お願い、助けてください」と懇願した。 彼の視線は運転席へ。運転手はハンドルにしがみつき、なんとか制御しようとしていた。


電話の向こうのオペレーターは落ち着いて対応を続けていた。彼女はポールがまだ幼い子どもだと理解していた。「そのまま電話を切らずに話し続けてくれる?」と優しく指示した。ポールは鼻をすすりながら、「うん」と答えた。 「運転手さんは今どう?大丈夫そう?」と尋ねるオペレーター。ポールの気持ちを落ち着かせることが、乗っている全員を助ける鍵だった。
素早い対応
涙混じりの呼吸で、ポールは必死に状況を説明しようとした。「運転手のゴバンダーさんが……多分、もうバスを制御できてません」と彼は嗚咽まじりに話した。 オペレーターはすぐに応答した。「わかったわ。バスはまだ動いてる?今どうなってる?」


「バスが道路の上でぐらぐら揺れて、スピードも出すぎてます!」と彼は震える声で叫んだ。「ゴバンダーさん……目がうつろで、しゃべれなくなってるんです」 涙を拭おうとしたが、止まらなかった。「心配しないで。今すぐ助けを向かわせるから。落ち着いて」とオペレーターは励ました。ポールは小さく頷き、息は乱れていたが、その言葉に支えられていた。
電話を切らずにいて
「そのまま電話をつないで、今起きてることを教えてくれる?」と、女性オペレーターは優しく言った。ポールは「うん」と小さく返事をした。 秒が何分にも感じられる中、ポールはオペレーターの落ち着いた声を頼りにしていた。ゴバンダーさんはまだ必死にバスを操ろうとしていた。奇跡的に、今のところ他の車にぶつかってはいなかった。


ルームミラー越しに、彼女は子どもたちを見ていた。ポールの位置からは、彼女の目が見えた。その目は数秒間、閉じてしまう瞬間があった。 何かがおかしい――眠っているのか、気を失いかけているのか?オペレーターにそれを伝えなければ。
何かがおかしい
幼いポールの頭は、今起きている事態をどうにか理解しようとしていた。見たところ、ゴバンダーさんは体調が悪いように見えた。 ポールは以前、重病のまま運転して道路の端に寄った叔父の話を聞いたことがあった。幸い叔父は無事だったが、行動の結果は重大だった。


今回も同じようなことなのだろうか?薬を飲み忘れた?それとも何かを飲んで、体が正常に動かなくなっているのか? 幼い頭で必死に考えながら、彼は電話に向かって言った。「運転手さん、病気かもしれません」 これでは、自分も、他の生徒たちも、無事には済まない――そう確信した。
彼女の目が閉じる
「もしもし……」彼は震える息の合間に言った。「ゴバンダーさんの様子が、本当に変です。目が何度も閉じてしまう。病気だと思います」 「わかったわ」オペレーターは電話越しに冷静を装った。「彼女に話しかけて。意識を保たせて、可能ならバスを止めてもらって」


でも、そんなことできるのか?ポールは電話を耳に押し当て、バスの前方へと向かった。 「まだ聞こえてますか?」とオペレーターに尋ねると、彼は左右に体を揺らしながら、必死に倒れないよう踏ん張っていた。 「ええ、聞こえてるわ。大丈夫よ」とオペレーター。 「運転手さんの様子を見てきます」とポールは伝えた。だが、その直後に通話が切れてしまった。
電話が切れる
ポールは目を見開いて携帯を見た。通話が切れたのではなく、バッテリーが完全に切れてしまっていたのだった。 母が「毎週日曜には充電しなさい」といつも言っていたのを思い出した。最後に充電したのがいつだったか、彼には思い出せなかった。 今となっては、代償を払うしかない。


「ゴバンダーさんを助けなきゃ」ポールは小さく自分に言い聞かせた。 父はいつもこう言っていた。「怖くなったとき、迷ったときは、一つのことに集中しろ。心を研ぎ澄ませて、その一つを乗り越えろ」 今日はその言葉の本当の意味を、彼自身が試す日だった。
決意
決意とアドレナリン、そして残り火のような恐怖が交じり合い、ポールはついにバスの最前部にたどり着いた。 「ゴバンダーさん!」彼は叫んだ。大丈夫なのか? バスはまだ高速道路をジグザグに走っており、エンジンは彼女がアクセルを踏むたびにうなりを上げた。 この悪夢は、いつ終わるのだろう?


ポールが近づくにつれ、状況の異常さがよりはっきりと見えてきた。最初は病気だと思っていた運転手――しかし、それは全く違っていた。 彼女の目は今、しっかりと前方のぼやけた道路を捉え、バスは交通の中を縫うように走っていた。 そして彼女はアクセルを踏み込み、笑った――いったい、何をしているんだ?
視線が合う
ポールはこの状況をどう理解すればよいのか分からなかった。彼はバスの運転手が重い病気で助けを必要としているのではと心配していた。彼女はインスリンの注射のようなものを打ち忘れ、苦しんでいるのだと思っていた。しかし今、彼は目の前の光景から何を読み取るべきか分からなかった。 彼はまだ考え込んでいた。その時、女性の目がポールの目と合った。


ミセス・ゴヴァンダーの目には不気味な炎が宿っていた。彼女はバックミラー越しにポールをじっと見つめた。そして微笑んだ。まるで道路から目を離していたことを思い出したかのように。ポールは今までこんなに背筋が凍るような光景を見たことがなかった。彼は一歩下がり、席に座り直し、携帯を起動しようとした。どうか、携帯が動いてくれますようにと、全身全霊で願った。
スリートライズ
携帯の電源が入るまでに三度試みが必要だった。その頃には、オペレーターがポールに数回折り返し電話していた。彼がかけ直そうとしたその時、電話が鳴った。オペレーターだった。ポールはすぐに応答した。しかし彼が話す前に、また携帯の電源が落ちてしまった。 この状況を対処するのは、自分しかいないと明らかになってきた。


心臓の鼓動が耳に響く中、ポールは再び運転手に近づいた。さっきの彼女の目を思い出さないように努めた。彼女がこれを故意にやっていたら?生徒たちを、もう二度と日の光を見られないような場所へ連れて行こうとしていたら?彼女が善意の人間でなかったら?ポールは震えた。
よからぬ考え
それまでポールは、ミセス・ゴヴァンダーが何か悪いことをしているとは考えていなかった。悪臭はバスの隅々まで充満し、その不気味な考えをさらに際立たせた。ポールの恐怖は倍増した。しかし、それと同時に決意と集中力も高まった。 それまでは彼女の無事を確認するために動いていたが、今は仲間の生徒たちを助けたいと思っていた。


父はいつも、「物事がうまくいかないときは、一つのことに集中しろ」と言っていた。ポールは今、それを実践していた。彼は席から立ち上がり、肘掛けを強く握りしめて運転手のもとへ向かった。何が起ころうと構わない。ただ、バスを安全に止めたい。それが彼の唯一の目的だった。
座っていなさい
ポールは何が起きているのかを確かめようと運転手のもとへ向かった。以前のように睨まれると思っていたが、今回は笑顔で迎えられた。 「座っていなさい」と彼女は答えた。「転んで怪我をしてほしくないの」 しかし、彼女の話し方にはどこか違和感があった。 「座って、いい?」と彼女は繰り返したが、ポールは従わなかった。


「本当に大丈夫か確かめたいんだ」とポールは毅然と言った。女性は二度彼を見てから眉をひそめた。「ええ」と彼女は答えたが、自信のなさそうな口調だった。「大丈夫よ。だから座って」 しかしポールは簡単には引き下がらなかった。座席をしっかり握ってバランスを取りながら、さらに食い下がった。
救おうとする心
助けは向かってきていたが、それまでの間に、ポールは自分とクラスメイトを救わなければならなかった。 「ミセス・ゴヴァンダー!」と再び呼びかけ、彼女がまた目を開けるのを見た。バスは相変わらず揺れながら進んでいた。 「助けを呼んでいます。でもバスを止める必要があります。道路の端に寄せなきゃ」 彼は大きな声で言った。


彼女はミラー越しに彼を見た。その目にあるのは困惑だった。まるで何が起きているのか全く分かっていないかのようだった。ポールは同じ言葉を繰り返した。やがて彼女はうなずいた。 苦労の末に彼女はブレーキを踏み込み、バスはようやく速度を落とし始めた。ただし、まだ左右に揺れていた。
起こしておくために
ポールは運転手に話しかけ続け、必死に彼女を起こしておこうとした。 臭いは依然として濃く、息をするのも辛いほどだった。 彼は、この臭いが彼女の突然の行動変化と関係あるのかもしれないと考えた。 オペレーターは他の生徒と連絡を取り、その子がポールに電話を渡した。 ポールが混乱した女性に話しかけると、オペレーターが尋ねた。 「バスは道路の脇に寄せてる?」


ポールの心臓は激しく脈打っていた。「寄せようとしてる」と答えた。 その間に、ミセス・ゴヴァンダーはついにバスを道路脇に止めることができた。バスが停車すると、子どもたちは皆、不安げに互いを見つめ合った。
充満する臭い
臭いはさらに強烈になり、バスが止まった後でも、ポールは恐怖を感じ続けていた。 ただただ家に帰って、両親を抱きしめたかった。こんなに怖いことは初めてだった。 「今は大丈夫?静かになったみたい」とオペレーターが言った。 ポールが重要な情報を伝える中、バスの中は静まり返った。


外では、何人かのドライバーがバスの様子を見ようと車を停めた。 ポールは電話を握りしめ、オペレーターは助けがすぐそこまで来ていると保証したが、時間が永遠のように感じられた。 果たして間に合うのか?
意識を失う
ポールが見上げると、運転手の女性は座席に崩れ落ち、目を閉じて口を開けていた。まるで眠ってしまったかのようだった。 ポールはこの臭いが原因なのではと考えた。 彼はそのことをオペレーターに伝えたが、その時は彼女が自分自身にそうしたとは思いもしなかった。

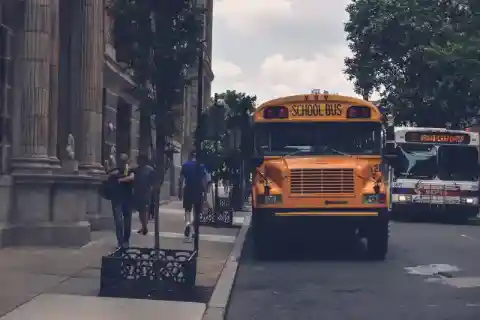
遠くからサイレンの音が聞こえてきた。次第に大きくなっていく。 ポールは安堵した。「サイレンが聞こえる。助けが来たと思う」とオペレーターに伝えた。 オペレーターは現場に到着したことを確認し、ミセス・ゴヴァンダーは再び目を開けた。
救助が到着
数分後、消防士と救急隊員が到着し、点滅するライトと緊迫した声が現場を包んだ。 彼らは迅速に状況を把握し、バスの換気システムを確認し、生徒たちを安全に避難させた。 新鮮な空気を吸えることが何よりの救いだった。 子どもたちは歩道に並び、次の指示を待った。


さらに遠くからサイレンの音が近づいてきた。 事情聴取のために刑事が向かっているのだった。 多くの子どもが関わる重大事件だった。 パトカーが停車したバスの後ろに停まり、サンチェス警官がバスに向かった。 ミセス・ゴヴァンダーは、まだガラスのような目で座っていた。
さらに裏がある
サンチェス警官は厳格で真面目な人物だった。ふざけている暇などない。彼女はバスに乗り込んだ。中には彼女とゴヴァンダー夫人の二人だけがいた。「マダム、車両から降りていただけますか?」サンチェス警官は、少しの懸念を滲ませながら、毅然とした声で言った。


ゴヴァンダー夫人は完全に正気を失っているようだった。席から立ち上がろうとしたが、何度か試みた末に、やっとのことで席を離れることができた。彼女は足元がおぼつかず、目を開けているのも辛そうだった。サンチェス警官はその様子をじっと観察しながら、後に続いてバスの外へ出た。何かがおかしい。
無礼な女
ゴヴァンダー夫人はバスを降りながら、今にも倒れそうにふらついていた。これは単に車両の問題による混乱ではないのでは?サンチェス警官は彼女の呼気の匂いに違和感を覚えた。「マダム、大丈夫ですか?」と問いかけたが、ゴヴァンダー夫人が言葉をろれつなく発した瞬間、警官は状況を悟った。彼女は飲酒検査を行った。


電話を握りしめたままのポールは、その様子を驚きと安堵の入り混じった表情で見守っていた。サンチェス警官の顔は懸念から厳格な不信へと変わっていた。ゴヴァンダー夫人は検査器に息を吹きかけ、結果を待った。結果は陽性——彼女は酩酊状態だった。彼女はバスに乗る前に飲酒していたのだ。そして、それが全員の命を危険にさらした。
報告書
消防隊が原因不明の異臭の調査をしている間、ポールは警察に事情聴取を受けた。少年は「匂いが鼻を焼くようでした」と言いながら顔を覆い、911に通報するに至った経緯を冷静に語った。彼の勇気と迅速な対応は、緊急隊員たちから賞賛された。


警官たちはバスを詳しく点検した。ボンネットを開けたが、エンジンには異常がなかった。タイヤも問題なかった。しかし、異臭はまだバス内に残っていた。やがて整備士が呼ばれ、調査の結果、異臭の原因がブレーキにあると判明した。彼女がブレーキを強く踏みすぎて、タイヤを摩耗させ、焼け焦がしていたのだった。
危険な運転手
事の重大さは、バスにいた全員に明らかとなった。ゴヴァンダー夫人は飲酒運転という重大な過ちを犯したのだ。彼女の行動は無責任で利己的であり、許されるものではなかった。警察は子どもたちの親に連絡を取り、迎えに来るよう要請した。


子どもたちは不安げに小声で話し合い、ポールは手を震わせながら、事の進展を911オペレーターに報告した。警官はゴヴァンダー夫人を逮捕し、子どもたちの安全を確保した。警察車両の後部座席に彼女が乗せられていくのを見届けながら、ポールはほっとため息をついた。こんな出来事が再び起こることは、もうしばらくないだろうと思えた。
無事に帰宅
ゴヴァンダー夫人が拘束されたあと、新しいバス運転手が到着し、子どもたちをそれぞれの家へと安全に送り届けた。子どもたちは、この悪夢のような出来事が終わったことに安堵していた。すでに午後5時を過ぎており、保護者たちはみな心配していた。


ポールの機転と勇気ある行動は、すぐにヒルズデール中に広まり、学校の友達や教師から称賛された。彼は「注意深い少年」としてさらに人気を高めた。帰宅したとき、両親は誇りと安心のあまり彼を強く抱きしめた。しかし、この出来事はポートランドのスクールバス運行体制に何か変化をもたらすのだろうか?
学校の懸念
この恐ろしい事件を受けて、学区はすぐに新しい安全対策を導入した。児童の送迎を監視するいくつかの代替策があり、そのひとつがバディシステム(仲間同士の相互確認)だった。そして即時対応として、午後のバスには予備の運転手を同乗させる措置が取られることとなった。だがこれは、依存症を抱える大人たちへの真の解決策になり得るのだろうか?


現在、ヒルズデール校ではポール・ウィティカー少年を「若き英雄」として称えている。危機に直面したとき、彼は勇敢に立ち向かい、大きな悲劇を未然に防いだのだ。彼は若き日の「健康と安全のポスター少年」となった。町の人々は今でも、彼の勇気に心からの感謝を捧げている。どこであれ、たとえスクールバスの中であっても、英雄は現れるものなのだと。